移住するなら食文化も確認しておこう
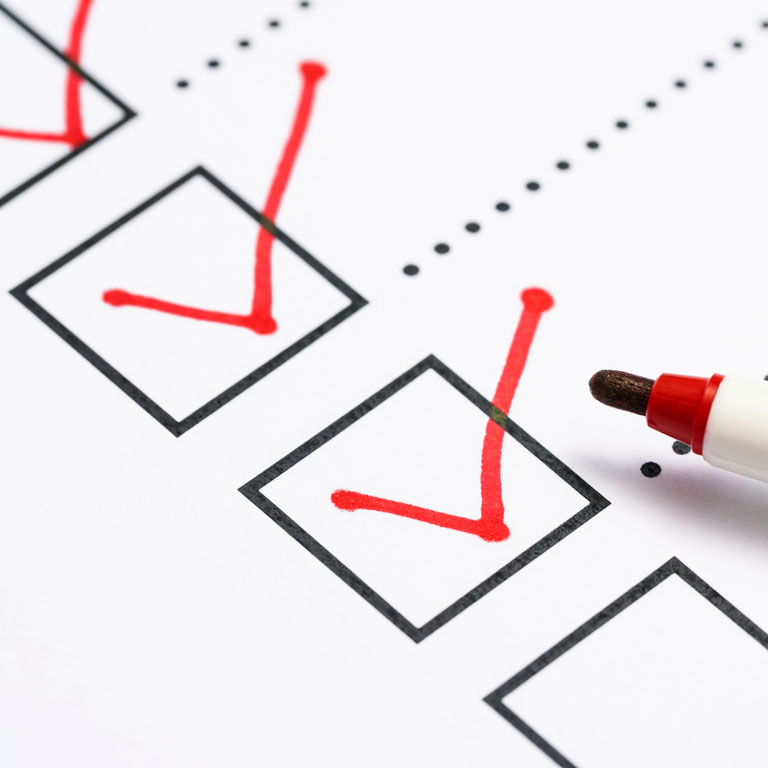
鹿児島の食文化は他の県と比較しても個性的です。どういった食文化が形成されているのでしょうか。
個性あふれる食文化
鹿児島は独特の気候と雄大な自然に恵まれている食の宝庫です。個性あふれる独自の食文化が根付いていますが、その中でも特に有名な伝統野菜と焼酎文化にスポットを当てて紹介します。
伝統野菜
鹿児島の伝統野菜を語る上で欠かせないのがシラス台地の存在です。シラスとは、火山が噴火した際に舞い上がった火山灰や小石が堆積されたものです。鹿児島で火山といえば桜島が思い浮かびますが、シラス台地は桜島の噴火によって生まれたものではありません。約2,900年前に錦江湾周辺で大きな噴火があり、周囲に火砕流が押し寄せ火山灰や軽石が降り注ぎ、広大な台地が形成されました。それが川の水によって削られ、現在のシラス台地になったのです。シラスは保水性が低く土壌が痩せているため、稲作には不向きです。また、鹿児島は台風が多く風雨や乾燥に強い農作物を育てる必要があったため、さつまいもや大根といった野菜の農作に着手したのです。これが、鹿児島の伝統野菜が誕生したきっかけです。
さつまいもに関しては、日本一の生産量を誇ります。1700年前後に琉球から持ち込まれたのがきっかけで、現在では「からいもごはん」や「からいもねったぼ」といった郷土料理としても親しまれています。桜島大根は200年以上前から栽培されており、大きなものでは20キログラムを超えます。シラスはミネラルを豊富に含んでいるため、それだけ大きくみずみずしい大根が栽培できるのです。鹿児島の伝統野菜についてより詳しく知りたい人は、以下のサイトを参考にしてください。
芋焼酎
鹿児島といえば芋焼酎をイメージする人も多いでしょう。16世紀の初め頃には穀類を原料とした蒸留酒も造られていましたが、稲作に適さない土地であることも関係し、米がベースのお酒ではなくさつまいもを使った芋焼酎が積極的に造られるようになりました。醸造を推し進めたのは島津斉彬ですが、当時は飲酒用に造られたわけではありません。西洋式の武器を製造するのに大量の高濃度アルコールが必要で、そのために醸造されたといわれています。稲作ができない薩摩藩にとって米は貴重品であり、その代わりに安価で手に入りやすいさつまいもを活用し、アルコールを製造することにしたのです。
全国的に人気の銘柄がいくつもありますが、かつては「芋焼酎は香りが強くて人を選ぶ」といったイメージがありました。しかし、最近では様々な食事と一緒に楽しめるようにさっぱりとした味わいのものも多くなっており、その人気はさらに高まっています。鹿児島の芋焼酎の種類や楽しみ方をより深く知りたい人は、以下のサイトを参考にしてください。
 鹿児島県酒造組合公式サイトへ
鹿児島県酒造組合公式サイトへ
-
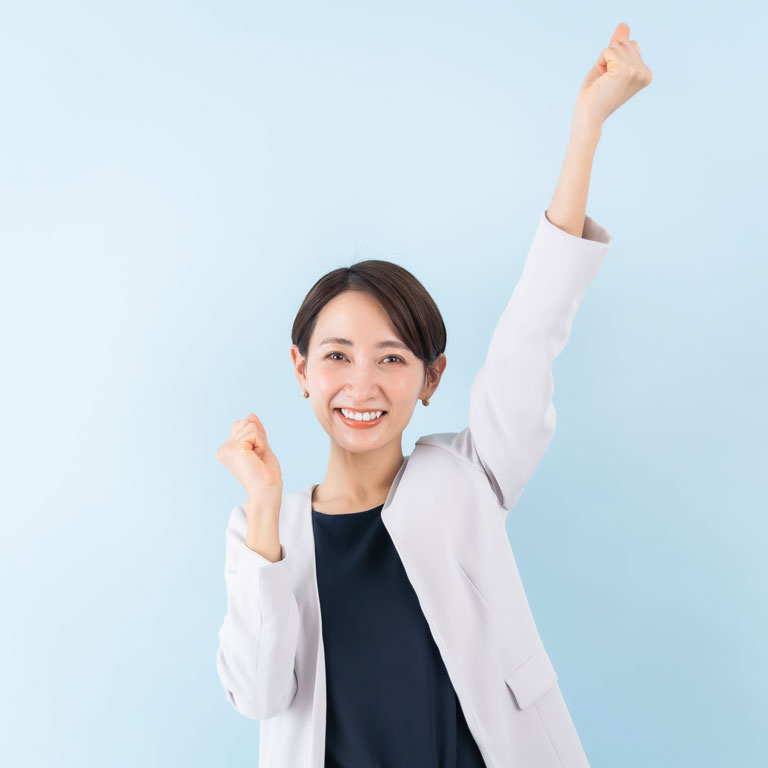 求人を探してみよう
転職エージェントで探す
転職活動を始める前に、転職エージェントに登録しましょう。効率的に鹿児島の求人を探すことができます。具体的なメリットやおすすめの転職エージェントを紹介するので、情報を集めている看護師はぜひ参考にしてください。
求人を探してみよう
転職エージェントで探す
転職活動を始める前に、転職エージェントに登録しましょう。効率的に鹿児島の求人を探すことができます。具体的なメリットやおすすめの転職エージェントを紹介するので、情報を集めている看護師はぜひ参考にしてください。
-
 医療事情について
看護師の転職動向は?
鹿児島には大小様々な医療機関が存在し、看護師の充実度は100%にやや足りない状況です。転職するなら今がチャンスでしょう。また、高齢化の影響から介護施設や訪問看護ステーションの求人も増えています。
医療事情について
看護師の転職動向は?
鹿児島には大小様々な医療機関が存在し、看護師の充実度は100%にやや足りない状況です。転職するなら今がチャンスでしょう。また、高齢化の影響から介護施設や訪問看護ステーションの求人も増えています。
-
 移住前に知っておきたい!鹿児島の基本情報
鹿児島の文化と遺産を辿ってみよう
鹿児島は様々な文化や遺産を有しており、移住先としてもおすすめです。観光スポットとして国内外から人気のエリアも多く、世界中の人を魅了しています。鹿児島の魅力について、より深く探ってみましょう。
移住前に知っておきたい!鹿児島の基本情報
鹿児島の文化と遺産を辿ってみよう
鹿児島は様々な文化や遺産を有しており、移住先としてもおすすめです。観光スポットとして国内外から人気のエリアも多く、世界中の人を魅了しています。鹿児島の魅力について、より深く探ってみましょう。

